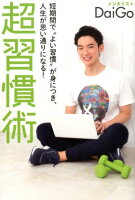こんにちは、ばちといいます。
if-thenプランニングを活用し、ブログの更新を続けています。
- if-thenプランニングについて分かりやすく学びたい!
- 目標を立てたはいいけど、なかなか達成できない…
- 今年こそは運動を始めるんだ!
この記事は、こういった方へ向けて書いています。
✔︎本記事の内容
- if-thenプランニングとは?
- if-thenプランニングの効果
- 【応用編】if-thenプランニングの効果を高める3つのコツ
新年の目標を立てたはいいけど、結局三日坊主で終わってしまった…。
あなたも、こんな経験ありませんか?
人間は、楽をしたがる生き物。
うまくコントロールしてあげないと、怠けてしまうんですね。
そこで役に立つのが「if-thenプランニング」による習慣化。
さまざまな論文により、目標達成率を2〜3倍高める効果があると確認されているテクニックです。
この記事では、そんなif-thenプランニングについて徹底的に解説します。

この記事を読めば、運動を習慣化するヒントを学ぶことができますよ!
if-thenプランニングとは?

イフゼンプランニングは、1980年代に社会心理学の分野で発見され、習慣化テクニックの王道といわれる最強のテクニックです。
その内容はとてもシンプルで、行動をするタイミングを事前に決めておく、というものです。
具体的には下記のとおり。
もし(if)Aになったら、そしたら(then)Bという行動をする
if-thenプランニングの活用例
シンプルゆえ、さまざまなことに活用ができます。
たとえば、
- 火曜日、木曜日の16時になったら、30分サイクリングをする
- おかしを食べたくなったら、代わりにみかんを食べる
- 上司にイヤミをいわれたら、1分間深呼吸をする
- 集中力が切れたら、5分間だけ作業を続ける
というように、運動やメンタル改善、仕事など、どんなジャンルでもOK。
アイデア次第で効果が倍増する、とても強力なテクニックです。
if-thenプランニングの効果

イフゼンプランニングについて、たくさんの実験が行われており、その効果は折り紙付き。
たとえば、ニューヨーク大学のピーター・ゴルウィツァー氏が94件の実験データを分析した論文(#1)では下記のように指摘されています。
イフゼンプランニングを使えば、目標達成率は大幅にアップする。その効果量は0.65だ
効果量とは、A(イフゼンプランニング)がB(目標達成率)にどれだけ影響をあたえるのかを表す数字。
1に近づくほど効果が高く、0に近づくほど効果が低いことを表します。
0.5を超えると優秀とされています。
なので、効果量0.65のif-thenプランニングは、積極的に取り入れるべきなんですね。
if-thenプランニングが効果的な理由
イフゼンプランニングがこれほど効果的な理由は、脳が「AならばB」という文章を理解、記憶しやすいためだといわれています。
人類は進化の過程で、生き延びることが最優先でした。
そのための行動は、自動的に反応するように進化してきたんですね。
たとえば
- 猛獣に遭遇したら、逃げる
- 食べ物を見つけたら、とりに行く
- 暗くなったら、眠る
というように、ある刺激を受けると、特定の行動がうながされるようにできているんです。
if-thenプランニングの最大のメリット
イフゼンプランニングのメリットは、無意識に行動できること。
目標を達成できない大きな理由のひとつが、「意思の弱さ」。
イフゼンプランニングを使えば、意志力を必要としません。
Aという刺激をきっかけに、Bという行動に意識が向くからです。
たとえば、16時になったら自動的に運動することを思い出し、準備を進めている、というようなイメージ。
事前準備に、ほんのひと手間くわえるだけで、目標達成率が格段に上がります。
習慣化にも応用できる
このような理由から、イフゼンプランニングは、習慣化したいときにも使えます。
社会心理学者のハイディ・グラント・ハルバーソンさんの実験を見てみましょう。
「運動を習慣にしたい!」という参加者を集め、2つのグループに分けたんです。
- グループ①:「運動を習慣化する」というシンプルな目標
- グループ②:「月曜日、水曜日、金曜日になったら、仕事の前に1時間ジムで運動をする」というif-thenプランニングの形の目標
というように、異なる目標を立て、習慣化に取り組んでもらいました。
すると、その結果は明らかで、
普通の目標を立てた参加者の39%しか運動を習慣にできなかったのに対し、イフゼンプランニングを使った参加者の91%が運動を習慣にしました。
ハンパない差ですよね…
習慣化が難しい運動も一撃です!
【応用編】if-thenプランニングの効果を高める3つのコツ


イフゼンプランニングの効果を、さらに20〜30%高める方法を3つ紹介します。
その①:具体性
いかに具体的に設定できるかが重要です。
たとえば
火曜日になったら、ランニングをする
と設定したとします。
ですが、これでは不十分で
- 火曜日の何時にやるのか?
- どれくらいランニングするのか?
がわかりません。
- いつ
- どこで
- 何をするのか
を明確に決め、脳が迷わないための導線づくりが大切。
この点をふまえ
火曜日の18時になったら、30分間いつものコースをランニングをする
というように、できるかぎり具体的に設定してみてください。
その②:障害への対策を立てる
事前に目標達成を妨げる障害を考え、その対策を立てておく、というテクニック。
- 達成したい目標を1つ選ぶ
- 目標達成の障害を考える
- その対策を考える
- 対策をイフゼンプランニングの形に落とし込む
の4ステップです。
ダイエットを例に、具体的に整理してみましょう。
ステップ①:目標を1つだけ選ぶ
絶対に達成したい目標をひとつ選んでください。
今回は、
半年後までに3キロ痩せて、ウエスト76センチのジーンズを履く
という目標を例にとります。
ステップ②:目標の障害を考える
- おかしを食べすぎてしまう
- 急な飲み会に誘われてしまう
- 運動する時間がない
3〜5つくらいを目安に書き出してみてください。
ステップ③:対策を考える
ステップ2であげた、障害の対策を考えます。
- 代わりにドライフルーツを食べる
- 飲み会には即答しない
- 運動するタイミングを決める
ステップ④:イフゼンプランニングの形にする
ステップ3の対策を、イフゼンプランニングの形に落とし込みましょう。
- おかしを食べたくなったら、ドライフルーツを3つまで食べる
- 飲み会に誘われたら、とりあえず「予定を確認する」と伝える
- 月曜日、水曜日、金曜日の18時に、30分間ランニングする
このように、目標達成を妨げる対策にイフゼンプランニングを使えば、より達成が近づきます。
その③:習慣を連鎖させる
行動と行動をつなげ、いい習慣を連鎖させるのもオススメ。
たとえば、
- AしたらBする
- BしたらCする
- Cしたら今度はDする
というように、ある行動を起点にして、どんどん連鎖させます。
いわゆるルーティン化ですね。
筆者の朝のルーティン
僕はこの方法を使って、朝のルーティンを決めています。
- 朝起きたら、コップ1杯の水を飲む
- 水を飲んだら、20分ランニングをする
- ランニングから戻ったら、シャワーを浴びる
- シャワーを浴びたら、10分間瞑想をする
- 瞑想をしたら、ブログを書く
というように、行動と行動を連鎖させ、習慣を作っています。
ポイントは歯磨きにあり!?
ポイントは、すでに習慣になっている行動に新しい行動を結びつけること。
その行動がきっかけとなり、無意識のうちに行動がうながされるからです。
朝の歯磨きがすでに習慣になっている方は、そこから運動や読書、副業などにつなげてみてはいかがでしょうか。
if-thenプランニングまとめ&参考本を紹介
今回は以上です。
まとめると
- if-thenプランニングは目標達成率が2〜3倍上がる最強テクニック
- 脳にとって最適なアプローチ
- 障害を事前に考え、具体的に対処
という内容でした。
あなたの目標達成を大きく近づけるif-thenプランニング。
ぜひ生活に取り入れてみてくださいね。
ちなみに、新しい習慣におすすめなのが瞑想です。
2年間で6000分瞑想した僕が、瞑想のメリットや継続のコツについて解説しました。
「なにかいい習慣を身に付けたい」という方はぜひ参考にしていただければ幸いです。
それでは!
✔参考にした本